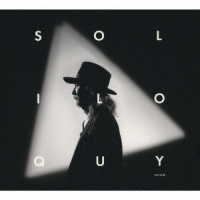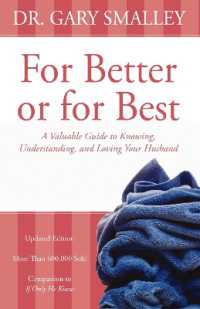内容説明
「僕は日本兵を殺した」アメリカのホスピスで見届けたのは、第二次世界大戦を生き抜いた人たちの最期だった。日本人が知らない「もうひとつの戦争」の記憶。
目次
第1部 太平洋戦争(良い戦争という幻想―「僕は日本兵を殺した」;記憶の中で生きる―「忘れないでくれ」;原爆開発にかかわった人―「誇りには思っていない」)
第2部 欧州戦線(アメリカの理想と現実―「僕たちは、なんのために戦っているのか」;女たちの戦争―「経験して初めてわかること」;ホロコーストの記憶―「ナチスが来る!」)
第3部 忘却と記憶(祖父が語らなかったこと;忘れられた中国人たち)
エピローグ その記憶は、私たちが自己満足と戦うことを可能にする
著者等紹介
佐藤由美子[サトウユミコ]
ホスピス緩和ケアの音楽療法を専門とする米国認定音楽療法士。バージニア州立ラッドフォード大学大学院音楽科を卒業後、オハイオ州のホスピスで10年間音楽療法を実践。2013年に帰国し、国内の緩和ケア病棟や在宅医療の現場で音楽療法を実践(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
※書籍に掲載されている著者及び編者、訳者、監修者、イラストレーターなどの紹介情報です。
感想・レビュー
※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。
trazom
81
音楽療法士である著者が、米国のホスピスで出会った戦争体験者の物語の記録だが、彼らの話をもとに、著者が、日本人として、一人の人間として悩む姿が心を打つ。ベトナム戦争と違い、米国では、第二次世界大戦は民主主義の理念を賭けて戦った良い戦争。でも、国家にとっての良い・悪いと、一人一人の国民にとっての価値とは別ではないか。一方、国家(特にナチス)に罪を擦り付け暗黙裡にその蛮行に加担した責任を回避するドイツ国民や、アジアの人たちへの行為を「社会的記憶喪失」として意図的に隠蔽している日本への疑問など、著者の思索は深い。2021/01/05
あやの
45
国家視点で見れば「輝かしい戦争」であっても、一人一人が体験したことは地獄以外の何物でもない。戦争経験者は、何十年も経って年老いても当時のことを語れない。彼らに寄り添う筆者の視点から、特に第二次世界大戦をどう捉えたら良いかを考察する。時間の経過もあり、出来事に対して忘却や修正が加わる。戦争とは、現代日本に生きていると他人事のように思えてくるが、勝ち負けに関わらず、戦争によって傷ついた心は一生完治することはない。世界では今も戦争が起き続けている。そこに直面した人々が安寧を得るのはいつのことなのか。2024/01/13
白玉あずき
45
「ホスピス物」は色々あるが、テーマを戦争の記憶にしたところが新鮮だった。ホロコーストの生き残り、マリーの終末期の悲惨さに言葉を失う。抑圧してきた恐怖の記憶に最後まで苦しみながら死を迎えるなど、なんという地獄だろう。「集合的記憶」の「社会的忘却」、「歴史修正主義」から来る自己肯定感。戦争の記憶を語るには避けて通れない。そこに踏み込んだ著者。そして挿入される広島でのオバマ大統領(当時)の演説。地獄の中で天を夢見ること・・・ 人の死によって失われていく記憶を、残される人間は素直に受け取りたい。2021/02/03
いろは
40
死の直前『走馬灯のように人生を思い出す』というのは、万国共通なのだな。米国でホスピス緩和ケアの音楽療法士をされている作者が、患者から聞いた戦争体験。アメリカ人からみた第二次世界大戦は、どんな風に見えていたのか。原爆開発に関わった人は、死を前にして何を思うのか。わかっているようでわかっていなかった戦争体験が、まだまだたくさんある。尊い思いを綴った本なので、★はつけないことにします。2021/05/23
たまきら
40
アメリカのホスピスなどで音楽療法士として活躍されている日本人女性が出会った戦争で傷ついたひとびと。ひょんなきっかけから東京大空襲の体験者を取材するようになった自分たちとの共通点を感じつつ、おざなりにされてきた魂を悲しく感じました。懸命に生き続け、最後の時を迎えるとき、自分の魂がもとめるものは何なんだろう?深く考えさせてくれる一冊です。素晴らしかった。読み友さんから。2021/01/22